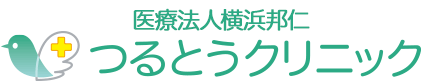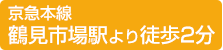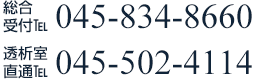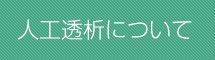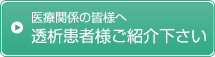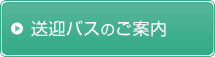動悸とは?考えられる原因と対策
動悸とは、自覚的に感じる心臓の鼓動の異常な速さや強さを指します。
多くの人が一時的に経験することがあり、必ずしも重大な病気を示すわけではありませんが、長期的に続いたり、他の症状を伴う場合には、何らかの循環器系疾患が隠れている可能性があります。
動悸の主な原因
動悸の原因は多岐にわたりますが、主に以下のようなものが考えられます。
心拍数の異常(不整脈)
不整脈は、心臓のリズムが乱れる状態を指し、脈が速くなったり、遅くなったり、不規則になることがあります。
これにより、動悸を感じることが多いです。
特に、心房細動や頻拍といった不整脈が原因となることがあり、これらは循環器内科での精密検査が必要です。
ストレスや不安
日常生活で感じるストレスや不安は、自律神経に影響を与え、心拍数が一時的に増加することがあります。
このような動悸は一過性で、リラックスすることで改善することが多いですが、慢性的に続く場合にはストレス管理や適切なカウンセリングが必要です。
カフェインやアルコールの摂取
コーヒー、エナジードリンク、アルコールなどの刺激物は、一時的に心拍数を上昇させることがあります。
これらの摂取量を減らすことで、動悸の頻度を下げることができるかもしれません。
貧血
血液中のヘモグロビンが不足することで、酸素供給が不十分になり、心臓が補おうとして早く鼓動することがあります。
動悸の他に、息切れや疲労感を感じる場合は、血液検査が必要です。
甲状腺機能亢進症
甲状腺ホルモンの過剰分泌により、新陳代謝が亢進し、心拍数が増加して動悸が引き起こされます。
この状態は、バセドウ病などの甲状腺疾患に関連しています。
薬の副作用
一部の薬、特に気管支拡張薬や降圧剤、抗うつ薬などが動悸の副作用を引き起こすことがあります。
新しく服用を開始した薬や、服用量の増減があった場合には、その影響を考慮する必要があります。
考えられる疾患
動悸を引き起こす可能性のある疾患には、以下のようなものがあります。
心房細動
不規則な心拍が特徴で、血栓や脳梗塞のリスクが高まります。
心不全
心臓のポンプ機能が低下し、血流が不十分になることで動悸が生じます。
頻拍性不整脈
異常に速い心拍が原因で、息切れやめまいも伴うことがあります。
冠動脈疾患
冠動脈が狭くなることで心筋への血流が制限され、動悸や胸痛が発生します。
バセドウ病
甲状腺機能が過剰になると、動悸が頻繁に生じます。
貧血
血液中の酸素運搬能力が低下し、心臓が過度に働くことで動悸が現れます。
受診のタイミング
動悸が単発的で短時間で治まる場合は、生活習慣の見直しやストレス軽減を試みることで改善することが多いですが、以下の場合には循環器内科への受診をおすすめします。
- 動悸が頻繁に起こる、または長時間続く
- 胸の痛みや圧迫感、息切れ、めまい、失神を伴う
- 既往歴として心臓疾患や高血圧がある
- 動悸に加えて、日常生活に支障をきたすような疲労感や呼吸困難がある
もし、動悸を感じながらも放置してしまうと、気づかないうちに重篤な疾患へと進行するリスクがあります。
早めに適切な治療を開始することが、将来の健康を守る上で重要です。
動悸に対する検査方法
循環器内科では、以下のような検査を行って動悸の原因を特定します。
- 心電図:不整脈の有無や心臓の異常を確認するための基本的な検査です。
- ホルター心電図:24時間心電図を装着し、日常生活での心拍の変動を記録します。
- エコー検査(心臓超音波検査):心臓の構造や機能を詳細に観察します。
- 運動負荷試験:運動中の心拍数や心臓の反応を確認し、運動時の動悸の原因を探ります。
気になる場合はご相談ください
動悸は一般的な症状ですが、その背後には重篤な疾患が隠れている場合もあります。
動悸を感じたときには、自己判断で放置せず、特に他の症状が併発している場合は早めに循環器内科を受診することが重要です。
専門的な検査を受け、適切な治療を開始することで、安心して日常生活を送ることができます。
定期的な検診や生活習慣の見直しも、動悸の予防や管理に役立ちます。
何か気になる症状があれば、ぜひご相談ください。
- HOME >
- 動悸とは?考えられる原因と対策